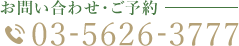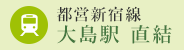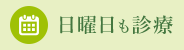急性症状から慢性疾患まで対応しております
 定期検診などで異常が見つかった場合や精密検査が必要な場合は、お気軽にご相談ください。また、のどの痛みや咳、発熱・鼻水・鼻づまり・痰といった風邪のような症状だけでなく、下痢や腹痛・吐き気・嘔吐・インフルエンザといった急性症状にも対応しています。その他、慢性疾患である糖尿病・高血圧・脂質異常・便秘・頭痛・貧血・アレルギーなどといった多くの疾患に対して診療ができます。気になる症状がございましたらお気軽に当院までご相談ください。
定期検診などで異常が見つかった場合や精密検査が必要な場合は、お気軽にご相談ください。また、のどの痛みや咳、発熱・鼻水・鼻づまり・痰といった風邪のような症状だけでなく、下痢や腹痛・吐き気・嘔吐・インフルエンザといった急性症状にも対応しています。その他、慢性疾患である糖尿病・高血圧・脂質異常・便秘・頭痛・貧血・アレルギーなどといった多くの疾患に対して診療ができます。気になる症状がございましたらお気軽に当院までご相談ください。
生活習慣病について
具体的には、高血圧・糖尿病・脂質異常症など、以前、成人病と呼ばれていた主に中年期以降に発症するありふれた疾患群です。
それぞれ単独でも恐ろしい病気ですが、高血圧、糖尿病、脂質異常症に肥満が加わると「死の四重奏」と呼ばれ、命に関わる危険が増します。
初期では症状の伴わない病気が多く、早めの受診が大切です。
以下のような症状がある場合には当院までご相談ください
- 発熱
- 腹痛
- 頭痛
- のどの痛み
- 疲労・倦怠感
- めまい・立ちくらみ・ふらつき
- 発疹
- 咳
- 胸焼け
- 吐き気・嘔吐
- 便秘・下痢
- 排尿痛・頻尿
- 関節痛・しびれ
- 動悸・息切れ
体の不調やちょっとした違和感を最初に相談できる診療科が内科です。特に明確な症状がなくてもご相談頂けます。例えば、急に太った・痩せたなどの体格の変化、疲れやすい・なんとなく体調が悪いといった違和感、健康診断では異常がなくても不安が残る場合もあります。ほんのわずかな不調から、深刻な疾患が見つかる場合もあります。早期発見ができることで簡単な治療で完治できる疾患もあるため、お気軽にいつでも受診してください。当院では、QOL(クオリティ・オブ・ライフ)の向上に繋がる内科診療を心がけ、地域の方の健康を守っています。ちょっとした不調や違和感といったお体や健康に関する不安やお悩みがありましたら、いつでもお気軽に当院へご相談ください。
内科の主な対応疾患
急性疾患
- めまい
- 風邪
- インフルエンザ
- 気管支炎
- 扁桃腺炎
- 肺炎
- 膀胱炎胃腸炎 など
慢性疾患
- 糖尿病
- 高尿酸血症(痛風)
- 高血圧症
- 脂質異常症(高脂血症)
- 便秘症
- アレルギー(花粉症)
- 貧血
- 頭痛 など